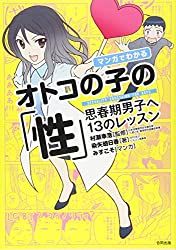泣き虫な娘が泣くのを防ぐ方法を見つけました!同じ目線でものを捉えてあげること
息子もそうでしたが、今3歳の娘はよく泣きます。
感情をため込まず発散できるのは良いことだ、とも言われますが、泣かれるとすごく疲れます。
泣かれ慣れると同情の感情もなくなってくる
たまに泣く子だと、泣いたら心配になると思います。
そんなに痛かった!?
そんなに辛かった!?
そんなに怖かった!?
って聞いてあげられると思います。
でも、毎日、何度も、ちょっとしたきっかけで泣かれ続けるとまたか!となる。
「どうしたの?」と聞くのも嫌になってくるし、
「そんなことで泣くの?」と思ってしまう。
娘が泣きそうな気配を感じたら「泣かないで!!!」と言ってしまうことが少なくありませんでした。
「もうママ疲れるから泣かないで…頼むわ…」と。
それでも泣いてしまったら、何を言っても何をやってもしばらくは収まらないので、諦めて放置することもありました。
痛いはずなのに泣かなかった!お風呂でのある出来事
そんな娘とお風呂に入っていた時のこと。
私がシャワーで髪を流しているところへ、娘が近づいてきました。
「もうちょっとで終わるから離れて待っててね」と言った直後、シャワーのヘッドがコツンと娘の肩に当たってしまったんです。
私の手にもそれなりの衝撃があったので、かなり痛かったはず。
「あああ!ごめん!!ごめんね!痛かったよね!!今のは痛いわ、ごめん!」と口をついて出ました。
そしたら、私のその焦りっぷりに驚いたのか、娘がぽかーんとしたような表情を浮かべてからひと言。
「え?だいじょうぶだよ?こんなの、ぜんぜんいたくないよ?ほら、ち、でてないよ?」
いや、今のは絶対痛い。
なのに泣かないどころか、痛くもないと言っている!
この不思議な現象は一体なんなんだ。
本人よりも先に、本人以上に驚き、痛みを代弁する
そんなに痛くないのに「いたい!」と言ったり、ちょっとしたことで泣いたりするのは、子どもなりのアピールなんですよね。
ねえママ聞いて!見て!わたしのことをわかって!というメッセージ。
そういうことは本などで読んでも、なかなか自分のケースに落とし込めなかったんですが、シャワーヘッド事件を経て少し理解できた気がします。
それ以降も、娘が泣きそうな状況に陥ったら、私が娘よりも先に、そして必要以上に大げさに心配したら、「こんなのだいじょうぶだよ」と言うようになりました。
ポイントは、”娘よりも先に”というタイミング。
どこかにぶつけたり、何か嫌なことがあったりした時、泣くまでに数秒の間があります。
娘が泣くべき事象を認識し、泣きの準備に入った時。
この初期での対応が重要です。
そして、もう1つのポイントは、”娘よりも大げさに”という程度。
そんなに痛くないでしょ、なんて思わない。
娘には10倍にも100倍にも1000倍にも感じる痛みセンサーがついている。
そのフィルターを通して心配し、驚いてみせること。
先日は、娘が足の指を机の角にぶつけました。
これは泣いても仕方ないやつ。
でも、このやり方で娘は泣きませんでした。(この時はこの戦術を意図的に使ったわけではなく、本当に心配したのですが)
「いたい、あかくなっちゃったね。でもだいじょうぶ」と。
同じ目線で共感してあげることが重要
改めて、今の自分の状況をわかってほしくて、これまでたくさん泣いていたんだな、と感じました。
ママにわかってほしくて泣く娘。
それがわからず大人基準で泣くに値するかどうか判断する私。
そして大したことがないのに泣かれることに疲れて無反応になる私。
ママに伝わらないのかと、さらにもっと泣く娘。
悪循環でした。
このことがようやくわかって、”娘よりも先に大げさに”をするようになったら、不思議と娘の基準でものが見えることが増えてきました。
娘ならこれは嫌だろう、これは痛いだろう、これは怖いだろう、というのが始まりでしたが、
こんなことが楽しいだろう、これが好きだろう、こうやって笑うだろう、というのにも広がってきました。
ネガティブな感情だけでなく、ポジティブなことにおいても、同じ目線で共感できるようになってきました。
その結果、娘が泣くことは減り、よく笑うようになった気がします。
そしてその影響は派生し、長く私の基準優先で育ててしまった8歳の息子の感情のぶれも減った気がします。
泣いてほしくなくてやり始めたことでしたが、子育てにおいて大切なことを気づかせてくれました。
↓ぽちっと応援お願いします★